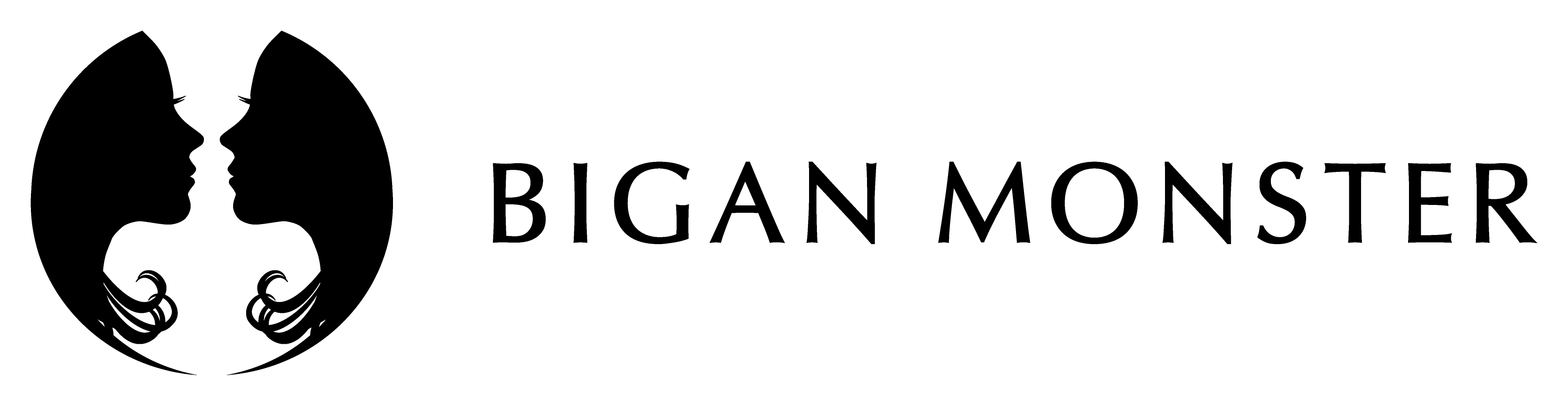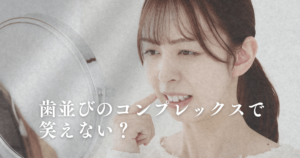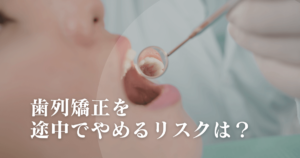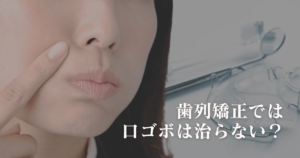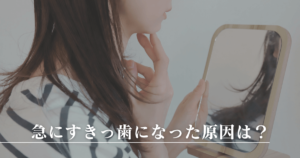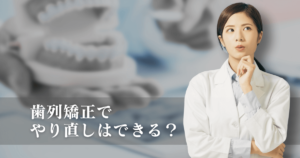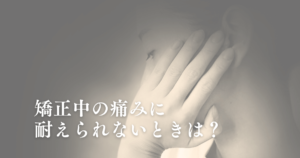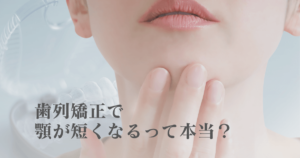受け口とは、下の前歯が上の前歯よりも前に出ている歯並びのことで「反対咬合」や「下顎前突」とも呼ばれます。
顎が前方に出やすく、しゃくれて見えることから、コンプレックスを抱える人も少なくありません。大人になってからでも治療できるか疑問を持つ人もいるでしょう。
この記事では、大人の受け口の治療、原因、および放置した際のリスクについて詳しく解説します。
大人の受け口を矯正する方法
顎が成長段階にある子どもと違い、大人の場合は骨格の成長を終えているため、歯列矯正によって上の前歯を前方へ、下の前歯を後方へ動かすことで受け口を治療します。
受け口には、歯並びや噛み合わせに問題がある「歯槽性(しそうせい)」と顎の成長に問題がある「骨格性」の2種類があります。骨格性の場合は、顎の骨の手術を併用した外科矯正が必要になるでしょう。
マウスピース矯正
マウスピース矯正は、歯並びや歯の傾きが原因の軽度の受け口を治療できる可能性があります。
マウスピース矯正の最大のメリットは「目立ちにくいこと」です。
特に、インビザライン(アメリカのアライン・テクノロジー社が開発したマウスピース型矯正治療法)は、薄くて透明性が高いプラスチック素材で作られています。そのため、ほかのマウスピース矯正に比べて審美性に優れ、希望する人も少なくありません。
しかし、マウスピース矯正は適応症例が限られるため、顎の骨格が原因の受け口や重度の受け口の場合は、治療が難しいケースもあるでしょう。
ワイヤー矯正
ワイヤー矯正は、歯並びや噛み合わせの悪さが目立ち、発音や外見に影響が出る中度の受け口を治療できる可能性があります。
中度の受け口の場合は、下の前歯を後方に移動させるためのスペースを確保する必要があり、抜歯するケースも少なくありません。そのため、矯正装置のブラケットとワイヤーを調整することで歯を大きく移動できるワイヤー矯正が適用されます。
マウスピース矯正に比べ、ワイヤー矯正は適応症例が幅広く、歯並びが原因の受け口であれば改善が期待できます。ただし、顎の骨格自体に問題がある場合は、外科手術が必要になるでしょう。
外科手術
受け口の要因には、遺伝や歯が生える位置、骨格などがあります。
歯が生える位置に異常がある場合は、歯列矯正のみで改善できる可能性がありますが、骨格自体に問題がある場合は、外科手術が必要になるでしょう。
受け口の外科手術は、下顎の骨を切断し、位置を調整します。その結果、噛み合わせが改善され、消化不良や頭痛、肩こりなどの全身の不調、見た目の問題を短期間での解消が期待できます。
ただし、外科手術には顔の痛みや腫れ、ダウンタイム、しびれや感覚麻痺、 心身のストレスなどといったリスクも伴うため、カウンセリングの際に歯科医師とよく相談して検討しましょう。
顎周りに特化した小顔矯正
受け口の外科手術にはさまざまなリスクを伴うため、治療に踏み切れない人もいるでしょう。もし外科手術を受けることが難しい場合は、顎まわりに特化した小顔矯正を検討することも一つの手段です。
小顔矯正では、顎まわりの骨格の歪みを整え、歯並びの土台となる顎が正常な位置に戻り、顔全体のバランスの改善が期待できます。
骨を切ることがないため、喉の圧迫や舌への影響、術後のダウンタイムなどの心配がなく、身体的・精神的な負担が抑えられるでしょう。
見た目の問題で悩みを抱えている人は、小顔矯正による根本的な歪みの改善を視野に入れることをおすすめします。
「小顔整顔専門サロン AGO TOKYO SALON」では、全身のバランスを整えることで、顎周りの筋肉や骨格が本来の位置に戻り、顎の前突が目立たなくするアプローチを取ります。特に、顎関節の不調や筋肉の緊張による顔の歪みがある場合に有効です。矯正の施術は痛みがなく、自然な形で顔全体を整えることが可能で、長期的に見ると、持続的な改善が期待できます。
大人の受け口矯正にかかる期間と費用の目安
受け口の歯列矯正や外科手術では、保定期間も含め、多くの時間と費用が必要になります。そのため、学業や仕事、ライフスタイルの変化などによって、計画通りに治療を進めることが難しいケースもあるでしょう。
効率的に治療を進めたい人や、経済的に外科手術を受けることが難しい人には、小顔矯正の併用がおすすめです。
矯正方法別の治療期間と費用相場
一般的に、矯正治療は保険が適用されないため、治療費は症例やクリニックによって異なります。
ただし、骨格的な問題が原因で機能に異常があり、条件を満たす場合は、保険が適用される可能性があります。適切な診断を受け、歯科医師に確認しましょう。
それぞれの治療方法の治療期間と費用の目安は、以下のとおりです。
- 治療期間:約2〜3年
- 費用:約40~100万円
- 治療期間:約1〜3年
- 費用:約30~150万円(表側矯正)、約40~170万円(裏側矯正)
- 治療期間:約1年半〜3年半
- 費用:約50~65万円(保険診療)、約140~400万円(自由診療)
小顔矯正の併用も検討
受け口の外科手術を検討する際、手術に伴うリスクや経済的な負担に不安を感じる人は少なくありません。また、外科手術は全身麻酔下で行われるため、症例や患者の状態によって3泊4日から2週間程度の入院が必要になることもあります。
そのため、手術を受ける時期の調整や仕事を休むことによる収入減が問題で外科手術を受けることが難しい場合は、小顔矯正の併用を検討することをおすすめします。
顎の骨格を本来あるべき位置へと整えることで、小顔効果が得られるだけでなく、安定した顎関節の動きをサポートする効果も期待できます。
経済的・身体的な負担を抑えつつ、歯列矯正の効果を最大限に引き出し、より美しい仕上がりを目指すことができるでしょう。
受け口になる原因
受け口の原因には、歯並びや噛み合わせ、遺伝、骨格の異常、歯並びに影響を及ぼす口腔習癖などがあります。
特に、幼少期の頃から下の歯を舌で押す癖や、下顎を前へ出して上唇を噛む癖などがある人は注意が必要です。
受け口の原因を理解することで、適切な診療が受けられるでしょう。
噛み合わせの不整合
上の前歯が内側に、または下の前歯が外側に生えてくると噛み合わせに異常が生じ、受け口になることがあります。
歯の生える位置や噛み合わせのずれが原因の受け口は、歯列矯正で改善できる可能性があります。
歯列矯正には、マウスピース矯正とワイヤー矯正があり、それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらの治療方法を選択すべきか悩む人も少なくありません。
治療の効果だけでなく、ライフスタイルや装着感も考慮し、歯科医師と相談しながら自分に合った治療方法を選択することが大切です。
ただし、顎の骨の位置や形に問題がある場合は、歯列矯正だけでは十分な改善が見込めないため、外科手術を検討しましょう。
顎の成長の不均衡
通常、上顎と下顎は成長に合わせてバランスよく発達しますが、上顎の発達不足や下顎の過剰な成長によって上下の顎のバランスが悪くなり、受け口になることがあります。
受け口の要因には、遺伝や歯並び、生活習慣、食べ方などが関係しています。特に、下顎の成長が優位に進むことがあるため、以下の生活習慣がある場合は意識して対策しましょう。
舌癖、口呼吸、頬杖をつく、猫背などの姿勢は、上下の顎の位置や成長に悪影響を及ぼす
よく噛まずに飲み込んだり、柔らかいものを好んで食べたりすると咀嚼回数が少なくなり、顎の成長が不十分になる
舌癖
舌で上下の前歯を押す舌癖は、受け口を引き起こす口腔習癖の一つです。
通常、舌の正しい位置は、口を閉じたときに舌先が上の前歯の付け根に触れ、舌全体が上顎についている状態を指します。しかし、舌先が下がり、下顎の前歯の裏側についた状態である低位舌にの状態になると下の前歯が押し出され、受け口になる人も少なくありません。
また、舌を前に伸ばし、前歯を押し出す舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)があると、上下の前歯が触れ合わない開咬になる可能性があります。 下の前歯に強い力が加わり、傾きが大きくなった場合は、受け口になるリスクが高まるでしょう。
舌癖の改善には、舌や口周りの筋肉を鍛え、舌の位置を正しくするMFT(Myofunctional Therapy:口腔筋機能療法)が有効です。
上唇を噛む癖
上唇を噛む癖がある人は、上の前歯が内側に押し込まれ、下顎が外側に突出するため、受け口を誘発するおそれがあります。
上唇を噛む癖は無意識に行われることがほとんどであるため、原因を把握し、以下の対処法で改善に努めましょう。
深呼吸やリラックスできる行動をとる
歯列矯正を行う
正しく唇を閉じるよう意識し、MFTを行う
また、癖を減らすためにリップバンパー(矯正治療で下顎の歯並びを整えるために使用する装置)の装着やガムを噛むことも有効です。
口呼吸
本来、人間は鼻呼吸が一般的ですが、口呼吸が習慣化している人も少なくありません。
口呼吸によって鼻の機能が低下し、鼻とつながっている上顎の成長が妨げられる可能性があります。また、口呼吸によって舌の位置が下がって舌が歯の裏につくようになり、下の歯が前に押し出されるため、受け口の悪化を引き起こします。
口呼吸の対処法は原因によって異なるため、以下の原因を把握して改善しましょう。
耳鼻科で治療を受ける
歯列矯正を行う
MFTを行い、舌や口周りの筋肉を鍛える
受け口を放置するリスク
受け口を放置すると、噛み合わせや歯並びが悪化し、見た目の影響だけでなく、発音障害、咀嚼機能の低下、虫歯や歯周病、顎関節症になるリスクが高まるなど、全身の健康にさまざまな問題を引き起こすおそれがあります。
受け口の場合は早めに歯科医院を受診し、適切な診断とケアを受けましょう。
見た目に影響を与える
受け口は、口元や横顔に影響を及ぼし、以下のような顔の特徴がコンプレックスの原因になることがあります。
- 顎が長くしゃくれて見え、Eラインが崩れる
- 下唇が厚く見えやすい
- 口角が下がり、老けて見える
- 眉から鼻下あたりが凹み、顔全体が平面的に見える
- 笑ったときに下顎の前歯が目立つ
見た目の悩みが自己肯定感の低下につながると、うつむきがちになったり、人との接触を避けたりするようになり、対人関係や社会生活に支障が出るおそれがあります。
受け口を改善することで、自分に自信が持てるようになり、自然な笑顔が増え、前向きに行動できるようになるでしょう。
発音や滑舌が悪化する
受け口は、上下の歯の間に隙間ができやすく、発音や滑舌に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、舌が十分に動かせないことが原因で、歯と舌先が触れるサ行、タ行、ナ行、ラ行の発音が不明瞭になる傾向があります。
自分でははっきりと話しているつもりでも、発音が不明瞭であるために何回も聞き返された経験がある人もいるでしょう。
滑舌の悪さがコンプレックスとなって自信を失い、人とのコミュニケーションを避ける人も少なくありません。
受け口を改善することで発音が明瞭になり、人との会話を楽しめるようになるでしょう。
咀嚼しにくくなる
受け口は、上下の歯が正しく噛み合わないため、前歯で食べ物が噛み切れなかったり、奥歯で食べ物をすり潰したりすることが難しくなります。
食べ物を細かくせずに胃や腸に運ばれると、消化器官に負担がかかり、消化不良や胃もたれを引き起こすリスクが高まるでしょう。
また、咀嚼回数が少ないため唾液の分泌が減少し、唾液による消化作用が不十分になります。
歯列矯正によって受け口を改善することで、歯全体を使って食べ物をしっかり噛めるようになります。その結果、食べ物を細かくかみ砕いたり、唾液の分泌が増えて食べ物の消化が促されたりするため、胃腸の負担を軽減できるでしょう。
虫歯や歯周病になるリスク
受け口は、口を閉じにくく口内が乾燥しやすくなるため、唾液の自浄作用が弱まり、虫歯の発症リスクが高まります。
また、噛み合わせの悪さが原因で一部の歯に偏って力が加わり、歯周組織に負担がかかるため、歯周病を引き起こすおそれがあります。
さらに、虫歯や歯周病を発症した場合、受け口によって治療の難易度が高くなるケースも珍しくありません。詰め物や被せ物をする際、噛み合わせの調整が難しくなったり、低位舌の習慣化によって舌が治療の妨げになったりする可能性があります。
歯のトラブルを予防するためには、定期検診や毎日の歯磨きによるセルフケア、歯列矯正が有効です。
顎関節症になるリスク
受け口によって噛み合わせのバランスが悪い状態を放置すると、咀嚼筋に負担がかかり、 顎関節に加わる負荷が大きくなるため、顎関節症を引き起こすリスクが高まります。
顎関節周辺の炎症や痛み、口の開け閉めがスムーズにできなくなる開口障害など異常を感じた際は、顎関節症を発症している可能性も否定できません。
人によっては、顎関節症が原因で頭や首、肩の痛み、めまい、耳なりなどが出現し、全身の健康に影響が出ることもあるため注意が必要です。
顎関節症が疑われる際は放置せず、専門家による適切な診療を受けるようにしましょう。
身体のバランスが悪化するリスク
受け口による噛み合わせの悪さが原因で、全身の筋肉への負担が左右非対称になり、首や肩、背骨などの骨格が歪み、姿勢の悪化につながることも少なくありません。
姿勢と歯並びは密接に関係します。特に、猫背の場合は顔全体が前傾するため、下顎が前方に突出しやすい状態になります。猫背の人は、以下の方法によって、正しい姿勢を意識しましょう。
- 壁に背中をつけて立ち、頭、肩、背中、腰すべてが壁につくように意識し、習慣化する
- スマートフォンを操作する際は、下を向く姿勢や長時間の使用を避ける
- 長時間の座り姿勢では、時間を決めて首を回したり、肩を上下に動かしたりして筋肉をほぐす
まとめ
大人になってからでも受け口の治療は可能です。受け口を放置した場合のリスクを理解し、早めに治療を受けましょう。
受け口の治療には、歯列矯正や外科矯正、小顔矯正があります。治療方法は、受け口の状態や骨格的な問題、患者の希望などによって異なります。
外科手術を受けることが難しい場合は、治療による心身の負担や費用を抑えられる小顔矯正を検討するとよいでしょう。